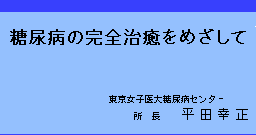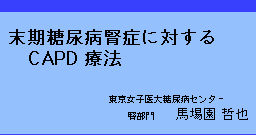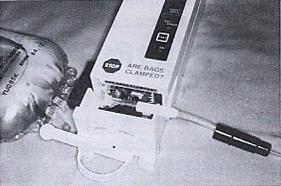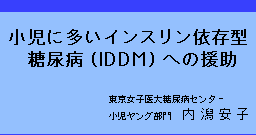DIABETES NEWS No.20
|
インスリン依存型糖尿病というタイプの糖尿病があります。若い時期に急激な発病をすること、遺伝がはっきりしないこと、インスリン療法が治療上、最重要となることなどの特徴を持っています。朝、夕2回あるいはそれ以上頻回のインスリン注射にもかかわらず、血糖のコントロールが困難なことが多いということになります。小児期に発病することが多く、比較的若いうちに腎不全を起こしてしまうこともあります。
◆ 日本でも増えたインスリン依存型糖尿病
このようなタイプは、白人に多いのですが、近年、日本でも増えはじめています。インスリン注射に加えて、腎の合併症が進行すれば血液透析を受けるということになります。このような患者さんは、多くの場合、社会復帰も困難になります。理屈の上では、膵臓と腎臓の移植に成功すれば、糖尿病からも血液透析からも開放されることになります。
この夢のような話が、ヨーロッパおよびアメリカの一流の糖尿病センターでは、すでに現実のものとなりつつあります。もっともすばらしい成績を出しているアメリカのマジソンという町のヴィスコンシン大学の場合、インスリン依存型糖尿病で腎不全となった患者さんに膵腎同時移植後、2年たってこの2つの臓器が正常に働いている率は 83%と発表されています。最近、4年後の成績でも 70%という話でした。患者さんは、まったく生れかわったように、インスリン注射も透析も必要なく、社会復帰も充分に出来ているといいます。
◆ 夢でない欧米の膵腎同時移植
日本では、糖尿病の場合、膵腎同時移植以前の腎移植もほとんど行われていません。糖尿病で腎不全になると、ほぼ 100%血液透析で治療し、腎移植は 0.1%以下です。ノルウェイでは 86%、スウェーデン 65%、フィンランド 53%の腎移植率に比べて、あまりにも大きい差といえます。東京女子医大でも最近、インスリン依存型糖尿病で血液透析を受けていた1人の患者さんが腎のみの移植を受けましたが、それだけでも透析中とは別人のように元気になりました。もし膵腎同時移植が出来れば、どれほど生活が充実することかと思います。
糖尿病の3大合併症の1つである糖尿病性腎症が進行すると、慢性腎不全(尿毒症)となり、透析療法や腎移植が必要となります。従来よりわが国では、末期腎不全の治療法として、主として血液透析が選択されてきました。しかし糖尿病の患者さんは、透析に至る時期には種々の全身合併症を有しており、血液透析が不適当であったり、困難であることが多いのが現状です。最近では、末期糖尿病性腎症の治療として、連続携行式腹膜透析(continuous ambulatory peritoneal dialysis、以下 CAPD)が注目され、これを用いる患者さんが徐々に増加しています。
◆ 末期腎症治療の現状
CAPD は、腹腔内にプラスチックバッグに入った腹膜透析液(1.0-2.0L)を貯留し、腹膜を介して尿毒症性物質や水分、塩分の除去を行うものです。自宅、職場、あるいは学校などで1日3~4回注液と排液を繰り返し、排液済みのバッグと新しいバッグを交換します。バッグ交換自体の操作は数分で終了します。血液透析では週2~3回病院に通う必要がありますが、CAPD の患者さんは月1~2回の通院ですみます。血液透析と異なり、24時間持続的に透析を行うため体重や血圧などの急激な変化がなく、またヘパリンなどの抗凝固剤を使用しないため、心臓の障害や眼底出血などを合併した糖尿病患者さんにおいても、安全に透析を行うことができます。
◆ CAPD とは
◆ CAPD の合併症――腹膜炎 CAPD の重要な合併症として、バッグ交換操作が不潔に行われた際などに起こる腹膜炎があります。そのため、糖尿病性網膜症による視力障害や、手指の筋力が低下した患者さんでは、従来はバッグ交換自体が不可能なため、CAPD の適応からはずされていました。しかし最近では、バッグ交換操作も改良され、このような患者さんでも安全に CAPD が継続できるようになりました。その1つに、右の写真のような、紫外線滅菌を利用したシステムがあり、現在東京女子医科大学糖尿病センターでは 10名の患者さんがこのシステムを使って CAPD を行っています。
紫外線滅菌を用いた CAPD バッグ
交換システム(UVシステム)
もし腹膜炎が起こった場合でも、入院の上腹膜透析液の中に抗生物質を注入することにより、通常は数日間のうちに軽快します。
末期糖尿病性腎症の治療に関するわが国の現状は血液透析主導型ですが、CAPD は医学的な利点のみならず、社会復帰の面でも有利であり、今後より多くの糖尿病の患者さんに、CAPD 療法が選択されるべきであると考えられます。
◆ 今後の展望
Diabetes News 19号で、わが国における小児期発見のインスリン非依存型糖尿病 (NIDDM) について、最近の知見が紹介されました。申すまでもなく、小児期に多いタイプの糖尿病は、インスリン依存型糖尿病 (IDDM) ですが、小児期 NIDDM と同様、IDDM も昨今増加の一途をたどっています。IDDM の発症機序には自己免疫が関与し、膵B細胞の破壊によるインスリン分泌の欠如が主役であることが今日明らかとなっています。膵臓の移植や、人工膵臓が手軽に利用できればよいのですが、残念ながら、現在 IDDM の治療はインスリンの注射療法しかありません。
◆ 自己免疫関与で起こる IDDM
また、IDDM は発症時間が小児期や成長の盛んな思春期であるため、患者さんは病気の治療だけでなく、就学、就職、結婚など社会的にたくさんの問題を抱えています。つまり、合併症をおこすことなく有意義な人生をおくるためには、インスリン治療の問題だけでなく、社会とのかかわりをスムーズにしていくためのさまざまな問題にたち向かわねばなりません。インスリン治療で血糖コントロールがきちんとできていれば、それはすでに健康と変わりない状態なのですが、これに対しての一般社会の理解は乏しく、病人扱いをされるというハンディキャップをおわされているのが現状です。このため、医療従事者は患者さんと手を組んで社会の状況を変えていく努力が必要です。
◆ さまざまなハンディキャップを負わされる
現在、社会の中で次のようないろいろな援助がなされています。これらの援助が有効に作用して、小児糖尿病者にとって、よりよい社会になることを祈ってやみません。
◆ よりよい社会にするための努力
1.厚生省は18歳まで費用を全額負担する小児慢性疾患を定めていますが、インスリン依存型糖尿病もこれに入っています。
2.日本糖尿病協会の中には、特に小児糖尿病対策委員会が設けられており、小児糖尿病者のお役に立とうとしています。"つぼみ"はその機関紙です。
3.医療サイドからは、日本糖尿病学会をはじめ多数の学会で、よりよい治療について研究しています。
4.毎夏、各地で小児糖尿病サマーキャンプが開かれます。糖尿病を理解させ、自己管理に必要な技術の修得に努力がそそがれています。
5.ヤング DM トップセミナーは各地区のサマーキャンプ卒業生の会として、池田義雄先生(慈恵医大)の御努力により発足しました。来年(平成2年)の第6回セミナーは東京女子医大の糖尿病センターが担当します。