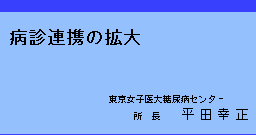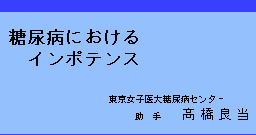DIABETES NEWS No.19
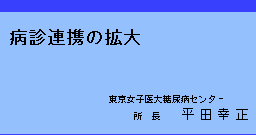
日本では一般的に病診連携の考え方は、疾患が重症化して入院を必要とするに至れば病院へ、外来では診療所で診療を続ける、そのために病院の医師と診療所の医師とが連携するというケースが多いようです。さらに糖尿病のように患者教育が治療の主体となる場合、患者教育の担当者となる看護婦、栄養士の病診連携が必要となります。その一環として私どもの糖尿病センターでは医師会のご協力をえて、コメディカルの人達に無料の講習会を開催しています。一人の患者が病診間で移動する場合、両者間で教育上、考え方の大きい差があることは障害となると思います。
先年来、精神的な大きい悩みに苦しんで当大学糖尿病センターへの入退院を繰返した患者さんがおりました。小規模であるだけに院長先生の人間愛に包まれたある病院への転院をおすすめしたところ、その後の社会復帰は驚くばかり速かだというお知らせをいただきました。
1ヵ月前、東京都内のある病院長先生からお電話がありました。若い女性の糖尿病昏睡で治療効果が出ない、何とかならないかということでした。すぐ転送していただき、強度の脳浮腫をCTという方法で証明し、翌日には意識の回復をみたのでした。ケトアシドーシス治療の経験の多いセンターでは、このような特殊例に対応出来なければなりません。また、4歳1ヵ月の小児のインスリン自己注射教育を他病院から頼まれて転院、1週間で自己注射可能にしたことがあります。このように病院間連携も、病院の専門別が進むにつれて、ますます必要となります。
少なくとも糖尿病の診療に関して、内科と眼科の診療所間の連携は、きわめて必要です。たとえば同じ内科診療所間でも、一人の患者をめぐって循環器を専門にされる診療所と糖尿病を専門とされる診療所との間の連携が必要となります。また眼科の診療所の間でも、硝子体手術が必要になれば手術用の機械を完備した眼科と連携するということが必要になります。
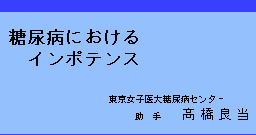
糖尿病におけるインポテンス(勃起障害)の頻度は3~5割の男性患者にあると言われていますが、この中には心理的なインポテンスも含まれています。
糖尿病性インポテンスの原因には神経、血管、筋肉(陰茎海綿体平滑筋と座骨海綿体筋)の障害が考えられますが、高血糖時の低テストステロンや心因も加味されて多因子によるものと思われます。しかし、いずれも血糖コントロールを良好に保っておけば完全に予防できる障害ですから、糖尿病になったからインポになるということは決してありません。
例えば、会社の検診で糖尿陽性を指摘され、糖尿病の疑いがあると言われただけでインポになってしまうような場合は、明かな心理的機能性インポテンスです。
インポテンスの原因として、意外に薬剤の関与が多いことは注意すべき点です。降圧利尿剤、向精神薬、抗潰瘍薬、制吐剤、ホルモン剤などでは勃起、射精、性欲などの性障害をときに起こすことが知られています。性障害の患者さんをみたら先ず服用中の薬についてチェックする必要があり、同時にテストステロンやプロラクチンの測定も必要です。
最も多い糖尿病性インポテンスは、ある程度勃起するが不十分で、持続しないというタイプです。焦りや不安から精神的緊張が高まれば高まるほど、ますます勃起機能は低下し、長年の経過から次第に性欲や治療意欲まで低下してしまうことが多いようです。
糖尿病性インポテンスの治療は、勃起機能がどの位残っているかで異なります。勃起機能検査として、私共では夜間陰茎膨張度検査やパパベリンテストを行っております。パパベリンテストは塩酸パパベリン 40mg を陰茎海綿体内に注射して勃起反応をみるものですが、心因性や神経性インポテンスでは良く反応し、治療的効果もあります。パパベリンに反応しない血管性インポテンスや神経・血管・筋肉の混合性インポテンスでは外科的治療の対象になり、日本でも一部の病院で実施しています。
ある程度勃起するが硬さが不十分で挿入できないという人には勃起補助具があります。これは、シリコン製のサックで陰茎を包むものですが、女性側の同意と協力が必要です。
全人的医療が叫ばれている今日、性の問題で一人悶々と悩む患者さんはかなり多いように感じられます。日本では今まで性をタブー視してきましたが、せめて糖尿病の方には開かれた心で接したいものです。

欧米における小児・ヤング糖尿病は、ほとんどがインスリン依存型糖尿病 (IDDM) です。一方、わが国では15歳を境としてインスリン非依存型糖尿病 (NIDDM) が増加し、IDDM よりも患者数が多くなっています。Diabetes News 第18号の「日本における MODY (maturity-onset type diabetes of young people) の特徴」の項にも書かれているように、昭和48年より全国の児童・生徒に対する健康診断の一環として検尿が義務づけられ、小児期発見 NIDDM はより一層発見されやすくなり、患者数が年々増加してきています。25歳未満で糖尿病になった患者では約半数が NIDDM 、残り半数が IDDM となっています。このように小児・ヤング糖尿病は欧米に比べ断然 NIDDM が多いといえます。
小児 NIDDM の特徴は糖尿病発見前あるいは発見時に肥満している患者が非常に多いということです。糖尿病発見時では、肥満以外に糖尿病症状がなく、また、病識が乏しい思春期・青年期を過ごしていくため、放置状態となりがちです。体重減少という症状が出現してはじめて病院に通院するようになります。このような放置状態で病院にこられた一部の方に、重篤な合併症が発見されることがあります。
この重篤な合併症の一つに増殖網膜症がありますが、1980年から1988年の9年間に当センターで初診した15歳未満発見 NIDDM 82例のうち、初診時にすでに増殖網膜症を認めた方が8例(10%)もいました。この方たちは糖尿病を発見されてから10年前後で、すなわち、20代の年齢で増殖網膜症になっていました。
小児 NIDDM の予後を同年代の IDDM と比較しますと、増殖網膜症を認める例が NIDDM で多数みられました。重篤な合併症を有する小児期発見 NIDDM は、もともと肥満していたにもかかわらず、体重減少をきたしてインスリン治療となっている方がほとんどでした。また、女性では妊娠中にはじめて進行した網膜症から糖尿病を発見される例があるなど、知らないうちに合併症が増悪していることが多くなっています。
学校検尿で糖尿病が発見されたら、放置することなく直ちに定期的に医療機関に通院させ、合併症を予防していくことが彼らの人生を豊かにする上で非常に重要であるといえます。
このページの先頭へ