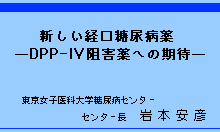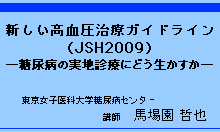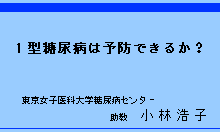| |  |
| No.110 | | 2009 May/June |
|
 |
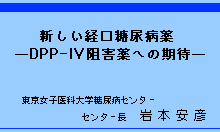
現在、日本で認可され幅広く使われている経口糖尿病薬は、スルホニル尿素(SU)薬、ビグアナイド薬、αグルコシダーゼ阻害薬、チアゾリジン薬、そして速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)の5種類です。これらはインスリン分泌促進系、インスリン抵抗性改善系、糖質吸収抑制系に大別され、それぞれの特徴を活かして、患者さんの病態に合わせて処方されます。
すでに海外で認可され、新しい経口糖尿病薬として注目されているのが DPP-IV阻害薬です。今回は、近い将来日本でも認可されることが期待されている DPP-IV阻害薬について簡単に紹介いたします。
ブドウ糖を経口投与した時と静脈内投与した時のインスリン分泌に差があることは古くから知られていました。経口投与したときに消化管(小腸)からインスリン分泌を促進する因子が分泌されることが想定され、"インクレチン"と呼ばれていましたが、その本態として GLP-1(glucagon-like peptide-1)と GIP(gastric inhibitory polypeptide)の2つの消化管ホルモンが同定されました。とくに GLP-1 は糖尿病治療薬として、さまざまな利点をもっていることが明らかとなり、GLP-1製剤として、海外ではすでに臨床で幅広く使用されています。DPP-IV阻害薬は、GLP-1 や GIP などの分解に関与する DPP-IV(dipeptidyl peptidase-IV)という酵素の分解を抑制することによって、活性型の GLP-1 の血中濃度を高め、インスリン分泌を促進させる結果、血糖低下作用を示す経口薬です。
DPP-IV阻害薬として、多くの薬剤が開発され、臨床試験が行われています。海外では、それらのうち、すでに2種類の薬剤(シタグリプチンとビルダグリプチン)が認可され、2型糖尿病患者さんの治療のガイドラインにも位置付けられています。SU薬に代表されるインスリン分泌促進系の経口薬で注意すべき副作用は低血糖ですが、DPP-IV阻害薬のインスリン分泌促進作用は血糖依存性であり、低血糖のリスクが低い点が特徴(利点)とされています。
インスリン分泌低下型というべき病態を示す2型糖尿病患者さんが多い日本やアジアの国々では、GLP-1製剤と並んで、DPP-IV阻害薬は注目すべき糖尿病治療薬であり、近い将来広く用いられるものと期待されています。
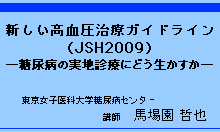
日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン(JSH2009)が5年ぶりに改訂されました。JSH2009 を糖尿病診療にどう生かすかについて、検討してみたいと思います。
糖尿病を合併する高血圧の降圧レベルについては、前回同様130/80mmHg未満とされています。この目標値を支持するわが国のエビデンスとして、端野・壮瞥町研究(2007)では、境界型耐糖能障害あるいは糖尿病患者で収縮期130mmHg以上および拡張期80mmHg以上の場合、120/80mmHg未満に比べ、心血管疾患による死亡が有意に増加していること、また糖尿病合併高血圧患者さんを対象としたわが国の大規模観察研究(Challenge-DM Study、2009)では、血圧を130/80mmHg未満に維持できた患者さんが、それ以上であった患者さんに比べ、心血管事故が有意に少なかったことがあげられます。
前回のガイドラインでは、第一次薬は ACE阻害薬、アンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)、Ca拮抗薬の3剤が併記されていましたが、今回の改訂で Ca拮抗薬は第二選択薬となり、ACE阻害薬と ARB が第一選択薬とされています。この点に関しては、議論があるかもしれません。
ACE阻害薬と ARB のいわゆるレニン・アンギオテンシン系抑制薬(RAS抑制薬)が、降圧効果を超えた臓器保護作用に秀でていることや、インスリン抵抗性改善などの点で、糖尿病患者さんに有利であることは間違いありません。ただし ACE阻害薬は、日本人を含めた東アジア人で空咳の頻度が高いことや、わが国で認可されている処方量では、Ca拮抗薬や ARB に比べ降圧効果が劣ること、一方 ARB は薬価が高いことが、それぞれの問題点としてあげられます。
一方 Ca拮抗薬の臓器保護効果は RAS抑制薬に劣るものの、降圧効果が高く、副作用が少ないこと、また最近アムロジピンの後発医薬品も認可されたことなどから、腎症や冠動脈疾患などの合併がない糖尿病高血圧患者さんでは、第一選択薬として残してもよいのではないかと思いました。
JSH2009 では、第一選択薬である RAS抑制薬で降圧が不十分な場合、Ca拮抗薬あるいは利尿薬を併用すると記載されています。すでに ARBと利尿薬の合剤がわが国でも使用可能であり、また今後 ARB と Ca拮抗薬の合剤も認可予定です。
糖尿病患者さんを約60%含めた ACCOMPLISH試験(2008)では、ACE阻害薬と Ca拮抗薬の併用は、ACE阻害薬と利尿薬の併用に比べ、心血管複合エンドポイントを約20%減少させたことが報告されました。一方同じ組み合わせで腎症患者さんの蛋白尿減少効果を比較した GUARD Study(2008)では、ACE阻害薬と利尿薬併用の優位性が明らかにされました。糖尿病高血圧患者さんにおける第二選択薬として、Ca拮抗薬と利尿薬のいずれを選択するかに関しては、腎症や大血管障害合併の有無、さらには薬価などを考慮する必要があります。
今回の改訂では、家庭血圧の管理目標値や、慢性腎臓病を合併した場合の血圧管理についても新しい記載がみられますが、紙面の都合で省略します。今後さらに国内外のエビデンスが蓄積され、それらの成果によってガイドラインが改訂、改良されることを期待したいと思います。
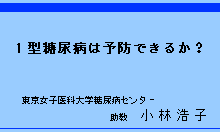
小児・思春期に1型糖尿病を発症する人は世界的には増加しており、発症率が高いフィンランドでは2型糖尿病とともに保健行政上大きな問題となっています。このような小児期発症1型糖尿病が欧米で増加しているメカニズムの解明は、遺伝要因の研究はもとより、最近は乳児の根菜類摂取との関連とか、生後2歳ごろまでの過剰な体重増加とか、環境要因の研究が大変進んできました。
1型糖尿病は、教科書的には HLAタイプなどの遺伝的要因にウイルス感染などの環境要因が重なり、自己免疫反応によって膵β細胞が破壊される疾患と考えられています。発症時症状が急激に出現することから、かつて発症直前までは正常で急性発症すると考えられてきましたが、発症する数年も前から、膵β細胞での炎症・破壊の進行とともにインスリン自己抗体、IA-2抗体、GAD抗体などの膵島関連自己抗体が陽性化し、その最終段階としてインスリン分泌が欠乏・枯渇し高血糖に至ることが、今では明らかにされています。つまり1型糖尿病を発症するかなり以前から体内での1型糖尿病発症への変化が始まっているというわけです。
フィンランドから興味深い論文が最近報告されました。これは、1型糖尿病感受性遺伝子はもっているがいまだ自己抗体陰性である多数の新生児を対象に、血液検査(主に血液中の脂質やアミノ酸の代謝産物)の結果と1型糖尿病発症の有無を前向きに調査した研究です。その結果、1型糖尿病を発症した子供は既に出生時から血液中のコハク酸とフォスファチジルコリン(PC)が低く、その後も中性脂肪とエーテル型リン脂質が低いことがわかりました。また、インスリン自己抗体や GAD抗体が陽性化する前に、グルタミン酸、分枝鎖アミノ酸が増加することもわかりました。
PC はコリンの主要構成成分で、コリンは生体内の重要な制御因子であると同時に VLDL と中性脂肪を低下させます。コハク酸は腸内細菌叢(腸管フローラ)より産生されますが、すでに1型糖尿病マウスの研究から腸管フローラと免疫システムの深い関係が証明されています。母親の妊娠中の食事や腸管フローラが新生児の血中コリンやコハク酸レベルに関連し、その結果、児のエネルギー代謝や免疫システムに影響を及ぼすことが推察されます。また、エーテル型リン脂質を代表するプラズマローゲンは細胞を酸化ストレスから防御する役目をもつことがわかっており、これが低下することにより膵β細胞が傷害を受けやすくなることが予測されます。また、グルタミン酸、分枝鎖アミノ酸の GAD抗体陽性直前の増加は、膵β細胞の恒常性を保つために、当初は生理的に生じる変化とも解釈できます。
これまでの多くの発症予防の研究は既に膵島関連自己抗体が陽性化した児を対象としていました。しかしながら、それ以前の出生時から、1型糖尿病を発症する児においては体内の代謝産物に特徴があることがわかりました。よって、出生後早期に血液中のリン脂質や腸管フローラのバランスを整えたり、ドコサヘキサエン酸の投与などが予防的治療として発案され、それによって1型糖尿病の発症予防や発症遅延が可能になるかもしれません。今回の研究は1型糖尿病の発症を予防するための介入試験の窓口をまた一つ拡げてくれたといえるでしょう。